東日本大震災アーカイブ
復興への闘い 震災3年の現実(11)第1部 市町村の苦悩 問われる説明責任
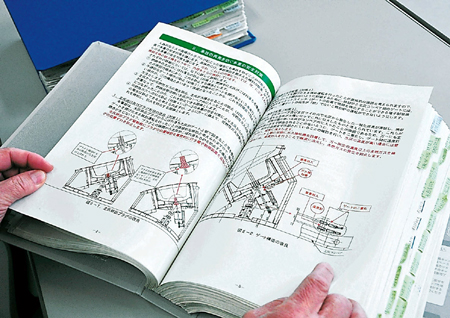
「こういう事故があってはならないんだ」
鮫川村役場で村長大楽勝弘(67)の大声が響いた。放射性廃棄物の仮設焼却施設爆発事故から4日が過ぎた平成25年9月2日。管理する環境省職員と運転を受託する会社の担当者を前に、怒りを抑え切れなかった。
施設は住民の「満場一致」の賛成を受けて稼働したわけではなかった。不安を訴える住民に安全性を説いてきた村の根拠は事故発生で崩れる。
事故の余波は、近隣自治体にも及ぶ。塙町は同4日、同省に安全対策の徹底などを求めた。いわき市の4市民団体が仮設焼却施設の廃止などを求める要望書を市に出す。市は同5日、徹底した原因究明と再発防止などを求める申し入れ書を同省に提出する。
村は事故発生の一報を防災無線で流さなかった。対応に批判が集まる。村は「住民の不安をあおってはいけない」と考えた。村地域整備課長の近藤保弘(58)は当時の判断を後悔している。「事故の程度にかかわらず知らせるべきだった」
東京電力福島第一原発事故発生後、さまざまな不安を抱えて生活する住民への配慮の難しさ。行政が少しでも油断すれば、住民との間に大きな摩擦が生まれるのを近藤は痛感した。
事故で増した施設に対する不信感をどう払拭(ふっしょく)するか―。事業主体はあくまで国だが、住民に説明する責任は施設設置を推進してきた村にもある。
村は住民への有事の連絡方法を改めた。事故の大小によらず、村は防災無線で発生の事実を流す。安全が確認されるまで随時、情報を伝える。大規模地震や施設の緊急停止ボタンを押した時など事故につながりかねない状況になったら、同省は村と、村が設けた仮設焼却炉監視委員会に即座に連絡する。
事故の再発防止策も見直した。人為的ミスを未然に防げるよう設備を改良する。安全管理態勢を強化するため、施設の作業人員を6人から14人と倍以上に増やした。
同省は25年11月14日に住民向けの説明会を開き、一連の対策を説明した。12月4日に監視委員会に最終報告する。了承を受け、同13日に復旧工事を始めた。
施設の運転再開に異議を唱える動きは続く。「爆発事故で村、環境省への不信感が強まった。再稼働したら、われわれと村との溝は埋まらないだろう」。住民有志でつくる「鮫川青生野(あおの)を守る会」の共同代表を務める金沢助右門(70)は引き続き運転中止を求める。
近藤は「疑問点、不審点があれば、これからも一つ一つ丁寧に答えていきたい」と住民に向き合う姿勢を強調する。
運転は今年3月までに再開される見通しだ。
県内の市町村は、東日本大震災や原発事故発生後、独自の判断を迫られる局面が増えた。住民生活に最も身近な自治体として住民からの期待は大きい。一方で、課題解決をめぐり、国や制度との闘いを強いられる。葛藤は続く。(敬称略)
=第1部「市町村の苦悩」は終わります=
(カテゴリー:復興への闘い)