東日本大震災アーカイブ
識者の目 福島医大医学部 甲状腺内分泌学講座主任教授 鈴木真一さん
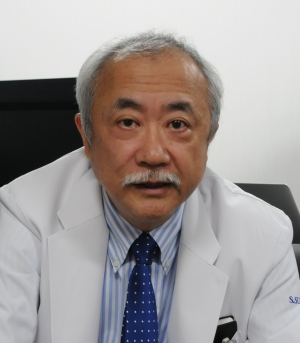
■十分に説明し治療法選択
−県民健康調査の甲状腺検査で見つかったがん細胞を遺伝子レベルで解析した。その結果は。
「福島医大で手術を受けた54人のうちの23人と、県民健康調査対象外の1人の合わせて24人分のがん細胞を調べた。9歳から22歳までだったが、チェルノブイリ原発事故後にベラルーシなどの子どもから見つかった小児甲状腺がんの遺伝子変異の特徴とは大きく異なった。具体的には、大人になって甲状腺がんを発症した場合に多く見られるBRAFというタイプの変異が多く見られ、全体の67%に上った」
−何を示唆しているのか。
「事故当時18歳以下だった子どもたちを対象に網羅的に精度の高いスクリーニング検査をしているために、通常なら大人になってから甲状腺がんとされるものが前倒しで早めに見つかっていると推測される。ただ、この結果だけをもって『放射線の影響ではない』という証明にはならない。チェルノブイリ事故後、約20年が経過して放射線と甲状腺がんの因果関係が分かっているので、引き続き慎重に分析を続けなければならないが、これまで『放射線の影響は考えにくい』としてきたことの裏付けの一つにはなる」
−チェルノブイリ事故後に多く見られた遺伝子変異は確認されなかったか。
「チェルノブイリではRET/PTC3という遺伝子変異が圧倒的に多かった。しかし、今回の24人からは一人も見つからなかった。チェルノブイリ事故の場合、空間放射線量よりも内部被ばく線量が大きく影響した。福島の場合は、生鮮食品の摂取や出荷の制限が効果的だったとされ、チェルノブイリほどの内部被ばくはしていないとみられている」
−今回の24例はどのような基準で選んだのか。
「平成25年末から26年初めにかけて治療した24例を調べた。医大の倫理委員会を通して同意の得られた人のみで、作為的に抽出したのではない。今後も、同意を得ながら解析を続ける。未知の遺伝子も含め多くのデータを集め、甲状腺がんの発生メカニズムについて分析していく」
−必ずしも治療の必要がないがんが見つかる「過剰診断」を懸念する疫学の専門家もいる。
「甲状腺がんが多く見つかることが、明確に不利益につながるのであれば『過剰』かもしれないが、そうではない。十分に説明をして治療法を選択しており、手術する人もいれば、経過観察にする人もいる。甲状腺や超音波検査に関する複数の学会などと協議の上、ガイドラインに沿って治療を行っている」
■経歴
すずき しんいち 会津若松市出身。福島高、福島医大医学部卒。同大外科学第二講座副部長や同大器官制御外科学講座教授などを歴任。平成24年6月から同大放射線医学県民健康管理センター甲状腺検査部門長。58歳。
(カテゴリー:震災から3年10カ月)