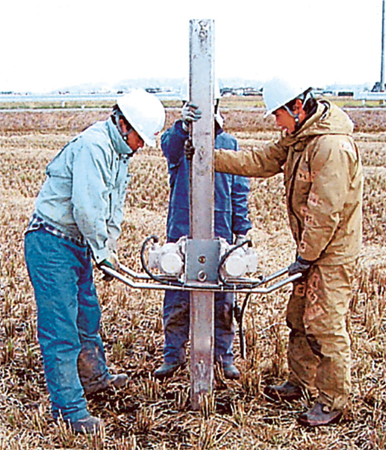【巨大津波 遅れた対策15】仕組み解明し後世に 確かさと素早さに悩み
「基本的に、違うことは起こらない」
茨城県つくば市にある独立行政法人・産業技術総合研究所の活断層・地震研究センター長の岡村行信(57)は貞観(じょうがん)11(869)年の地震と、昨年3月11日の東日本大震災の地震のメカニズムは「ほぼ同じ」と見ている。歴史記録に残る地震や津波の痕跡を追い、科学的に全容を解き明かし、長期的な対策に反映させる必要性を指摘する。
■数100年間隔
岡村は貞観と東日本大震災の地震との間で、室町時代(1300年代~1500年代)に大地震があったと考える。東北地方や現在の山梨県などで地震に関する歴史記録が残る。
研究機関による津波堆積物の調査でも、貞観地震より後の時代の地層から痕跡が見つかっている。ただ、時代が進むにつれて、津波の堆積物は地層の表面近くに位置する。水田の地層は耕され、確証は得にくくなる。
産総研も調査しているが、現段階で全容解明に至っていない。岡村は「堆積物が残っていないと攻めようがない」と悩ましい表情を浮かべる。
ただ、貞観と室町、東日本大震災の3つの地震が同じメカニズムで起きたとすれば、500~600年間隔で巨大地震が発生してきたことになる。岡村は「相当先かもしれないが、間違いなく繰り返す」と語り、研究と対策を後世につないでいく必要性を説く。
一方、大震災の余震は今後数10年にわたり、注意が必要とされる。三陸地方に津波被害をもたらした明治29(1896)年の明治三陸地震と、昭和8(1933)年の昭和三陸地震は40年近く発生時期が離れているが、発生のメカニズムから関係があるとされる。「時期の予測は困難だが、安心だとはとても言えない」と警鐘を鳴らす。
■信頼
「研究結果が固まる前に情報が広がると誤解を生む。だが、じっくり検証していては時間がかかってしまう」。岡村は情報発信の信頼性と迅速性の狭間(はざま)で思い悩む。研究機関には素早い情報提供が求められるが、津波の痕跡から発生時期や浸水規模を割り出し、襲来時と現在の地形の違いを踏まえて危険性を提示するには多くの時間が必要となる。
東日本大震災の発生後、全国的に地震と津波に対する関心は極めて高まった。研究者が明確な確証を得ていない段階で想定を口にすることで、不安を増長するケースも出ているという。「精度を維持して発信しないと、研究者の信頼が損なわれかねない」。岡村は危機感を募らせる。(文中敬称略)