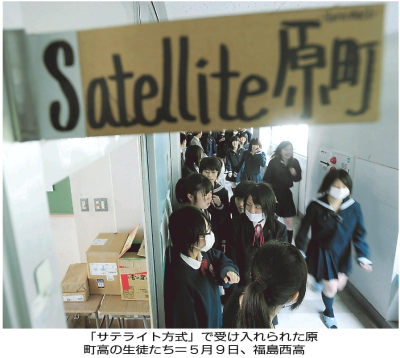【農地の表土剥ぎ取り】処理法に苦慮 費用負担、誰が

農地の除染法について実証実験を続けてきた農林水産省は14日、表土の剥ぎ取りが最も効果的だとする結果を発表した。収穫の秋を間近に控え、日々、発表される県の放射性物資の検査結果に神経をとがらせていた農家には久々の「朗報」となる。しかし、表土の処理法や、除去費用を誰が負担するのかについて明確になっておらず、自治体から批判も漏れてくる。
■また難題
「また難題が増える。どう対応すればいいのか...」。農林水産省が発表した農地の除染法の内容を聞いた福島市政策推進部の職員は頭を抱え込んだ。
畑から除いた土を、どこに仮置きするのか。農水省は「市町村に任せるしかない。方法は思い付かない」と苦しい説明に終始する。
市は住宅地などの除染作業で発生した土砂などの廃棄物を、市内数カ所に設ける仮置き場に保管する方針。しかし、住民の反対も予想されることから候補地選定に苦慮しているのが実情だ。
市内大波地区で行った1カ月間の除染作業では、土のう8700袋分の土砂が出た。同地区だけでも今後、3万袋増える見込みだ。市内の農家が一斉に表土除去を開始すれば、どれほどの土砂が出るのか見当も付かない。
■国が負担を
農水省は土1キロ当たりの放射性物質濃度が5000ベクレル以上の農地の場合、国が除染の主体となる方針を示した。しかし、土1キロ当たり5000ベクレル未満について明言を避けており、費用が農家負担になる可能性も浮上している。
東京電力福島第一原発事故による特定避難勧奨地点を抱える伊達市霊山町小国地区。農家男性(55)はモモ、コメなどを計約130アールで栽培している。
風評被害でモモも大きく値崩れし、今年の売り上げは落ち込んだ。田畑など農地全てを自費で取り除くことは不可能だ。「自分で除染すれば費用も時間もどれだけかかるか、国でやるのは当然」と言葉に力を込めた。
■一刻も早く
農水省は国の責任で除染すると約束した土1キロ当たり5000ベクレル以上の農地について、着手する時期を明らかにしていない。
対象となるのは警戒区域、飯舘村などの計画的避難区域や、緊急時避難準備区域内の一部などとみられ、関係自治体から早急に作業を始めるよう求める声が上がっている。飯舘村産業振興課の職員は「国の責任でやってもらえれば、話が早く進むのではないか」と期待する。
一方、村内に土1キロ当たり5000ベクレル以上の農地はないものの、今年度内に村内への帰還を目指す川内村の遠藤雄幸村長は「一時帰宅のたび、荒れた農地を目の当たりにしてきた。昔の環境を取り戻してほしい。国は5000ベクレルという基準にこだわらず支援すべきだ」と訴えた。
こうした願いを前に、農水省は「開始時期は早くとも年明けになる」と釈明している。
【背景】
飯舘村などでは「計画的避難区域」設定後の5月から、農林水産省、県、大学などが水田や畑で固化剤を使った表土剥ぎ取り、代かきによる汚濁水の排水実験を行ってきた。土木機械を使って削った水田で水稲栽培を行い、コメへの放射性セシウムの吸収実験も進めてきた。同村の菅野典雄村長は今後、2年後をめどに帰村する考えを打ち出しており、いかに効果的に除染を進めるかが住民が帰宅する上での鍵を握っている。