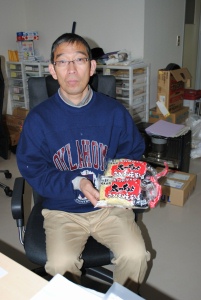富岡「桜染め」復活へ いつか夜の森のサクラで...

■郡山に工房 秋田の名所が枝提供 避難生活の励みに
サクラのトンネルで有名な富岡町の「夜の森公園」のサクラを活用した特産品「桜染め」が復活に向け動きだす。町社会福祉協議会が多くの町民の避難先となっている郡山市に工房を作る。特産品を守るとともに、避難が長期化する町民の雇用と生きがいづくりにも結び付ける考えだ。警戒区域にある町のサクラは使えず、サクラの名所の縁で秋田県仙北市角館町から枝などの無償譲渡を受ける。「いつか夜の森のサクラで...」。新たな希望が避難生活の励みになる。
「富岡のサクラは使えないが、思いは込められる。技術を伝え、また古里のサクラで染める日を待ちたい」。桜染めに携わってきた、町内の知的障害者入所更生施設「光洋愛成園」の生活支援員、瀬田川和枝さん(47)は特産品の復活に町復興を重ね合わせた。
桜染めは、町観光協会の企画で、平成17年に同施設の入所者約10人が「工房さくら」をつくって取り組み始めた。瀬田川さんは入所者と手を携え、商品の品質アップに力を注いできた。
町内で平成18年に開かれた「さくらサミット」の出席者に記念品として配られ、物産プラザふくしまの「ふくしま特産品コンクール」工芸・雑貨部門で大賞を受けるなど次第に認知度が上がった。その後、地元の老人クラブも商品作りに乗り出し、生産量は拡大。桜染めの体験教室は観光客の人気も集めた。
東京電力福島第一原発事故が全てを奪った。工房さくらのメンバーを含む入所者は群馬県高崎市の施設に避難し、瀬田川さんも付き添った。サクラがある古里には立ち入ることもできず、桜染めは存続の危機に陥った。
「富岡はサクラの町。桜染めを復活させよう」。昨秋になり、町社会福祉協議会が運営する郡山市の生活復興支援施設「おだがいさまセンター」の職員から声が上がった。
仮設住宅や借り上げ住宅で暮らす町民は高齢者が多い。閉じこもりの解消や生きがいづくりが課題となっていた。町民が働ける場として桜染めの工房の設置計画が立てられた。
場所は郡山市内で、町民約20人を雇用する方針。県の補助金を受けることが内定した。「避難生活を強いられる町民にとって希望の光になる」。計画を担当する協議会職員の迫英之さん(40)は工房の場所選定など、準備作業に追われる。
瀬田川さんも講師として町民に技術を伝える。被災地支援を申し出た人間国宝の染織家志村ふくみさん(京都)や、桑折町の草木染めの職人の協力を仰ぎ、ブランドに磨きを掛ける。仙北市角館町からは軽トラック1台分のサクラの枝などの提供を受けている。施設完成を待ち、秋ごろにはストールやバッグなどの製作に入る。
光洋愛成園の入所者も避難先の施設内で桜染めを始められるよう準備している。瀬田川さんは「県内に戻ったら、すぐに参加できるよう、しっかり練習をしておきたい」と、目標を見定めた。
■20日町民説明会スタッフを募集
おだがいさまセンターは20日、桜染めの町民説明会を開く。工房の設置を伝えるとともにスタッフを募集する。
※桜染め
サクラの枝や葉を2センチ程度に切り、熱湯で30~40日間煮込んで抽出した染め液に、布などを浸して3~4日かけて色を付ける。季節ごとの枝の生育度合いなどによって濃淡の異なるピンク色に染め上がるのが特徴だ。富岡町内のサクラの木の剪定(せんてい)などで出る大量の枝や葉を有効活用して特産品を作ろうと平成17年に始まった。