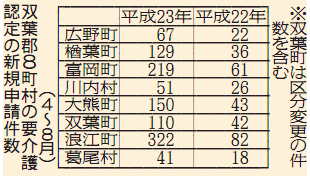【原町の5小中校再開】児童生徒6割戻らず 除染でも残る不安

東京電力福島第一原発事故による緊急時避難準備区域の指定が解除され、17日に旧区域内の自校で約7カ月ぶりに再開された5つの小中学校では久しぶりの校舎を喜ぶ児童生徒の笑顔であふれた。一方、多くの児童生徒は市外に避難したまま。従来の学校生活を取り戻すまでには課題は多く、市や学校関係者、保護者らの手探りが続く。
■目立つマスク姿
7カ月ぶりの登校となった17日朝、南相馬市原町区の原町一小の校門前には児童を送る保護者の車が列をつくった。車を降りる児童の中にはマスクを着ける姿も目立った。
市は緊急時避難準備区域の解除を前に、各校の校庭の表土剥ぎ取りや校舎の洗浄、学校から半径約200メートルの通学路などの除染に取り組んできた。保護者や教職員、地域住民も協力し、この日を迎えた。
再開した小中学校5校には震災前、児童生徒2174人が在籍していた。だが、再開後に通い始めたのは886人と約4割にとどまった。
原町一小の校庭地上一メートルの空間放射線量は8月初旬、毎時0.60マイクロシーベルトだったが、毎時0.14マイクロシーベルトまで低減した。それでも放射線に対する根強い不安から避難先から戻るのをためらう保護者は多いという。同小一年生を送りに来た母親(33)は「いくら除染作業で線量が下がっても、子どもの健康への影響に関する心配は消えることはない」と複雑な表情を見せた。
■再開できない
9月末まで避難所だった原町二中では、本校に初登校した1年生の生徒がクラス分けの後、机やイスを教室に運び入れた。1年の木幡美桜さん(13)は「共同で使っていた体育館では、思うような練習ができなかった。今後は体育館が自由に使えるのでバレー部の練習を頑張りたい」と喜ぶ。
一方、再開した5校以外に旧避難準備区域内には小中学校が7校ある。7校の学区に自宅がある児童生徒は、スクールバスで旧区域外の鹿島区に設置されている間借り校舎に引き続き通っている。
太田小など4校は3学期の再開を目指しているが、学区内に特定避難勧奨地点が点在する石神地区の3校については再開のめどが立っていない。
このうち、石神一小では、校舎や校庭の除染作業が進み、校庭の空間放射線量は高さ1メートルで毎時0.15マイクロシーベルトと決して高い水準ではない。しかし、避難世帯や高齢者の1人暮らし世帯などでは除染作業に限界があり、除染作業が手つかずの場所が点在する。市学校教育課の担当者は「通学路や自宅など、子どもの生活環境全体の改善が不可欠で、現段階では再開できる状況にない」と実情を明かす。
■進まぬ作業
旧区域内の各校の通学路では、市が依頼した建設業者や地域住民らが高圧洗浄機での除染作業を進めている。だが、学校から各家庭に至る通学路の総延長は長大で、除染のスピードが上がらないのが現状だ。
市は本格的な除染に向け、現在、新たな除染計画の策定を進めている。「国の方針を待っていたのでは何もできない。子どものためにも継続的に通学路の除染に力を注ぎたい」。市の担当者は早期の全校再開を目指す。
一方、南相馬市以外で緊急時避難準備区域だったエリアの小中学校は田村市で3校、広野町で2校、川内村で2校あるが、いずれも自校での再開は見通せない状態だ。
【背景】
南相馬市内では小中学校合わせて22校あり、東京電力福島第一原発事故を受け、警戒区域の5校と、緊急時避難準備区域の12校は原発から30キロ圏外の市内鹿島区で校舎を間借りするなどして授業を行ってきた。原発の収束見通しが立ったことなどから9月末に緊急時避難準備区域が解除された。同区域内では学校運営が認められていなかった。旧区域の学校では再開を見通して除染が急ピッチで進められてきた。